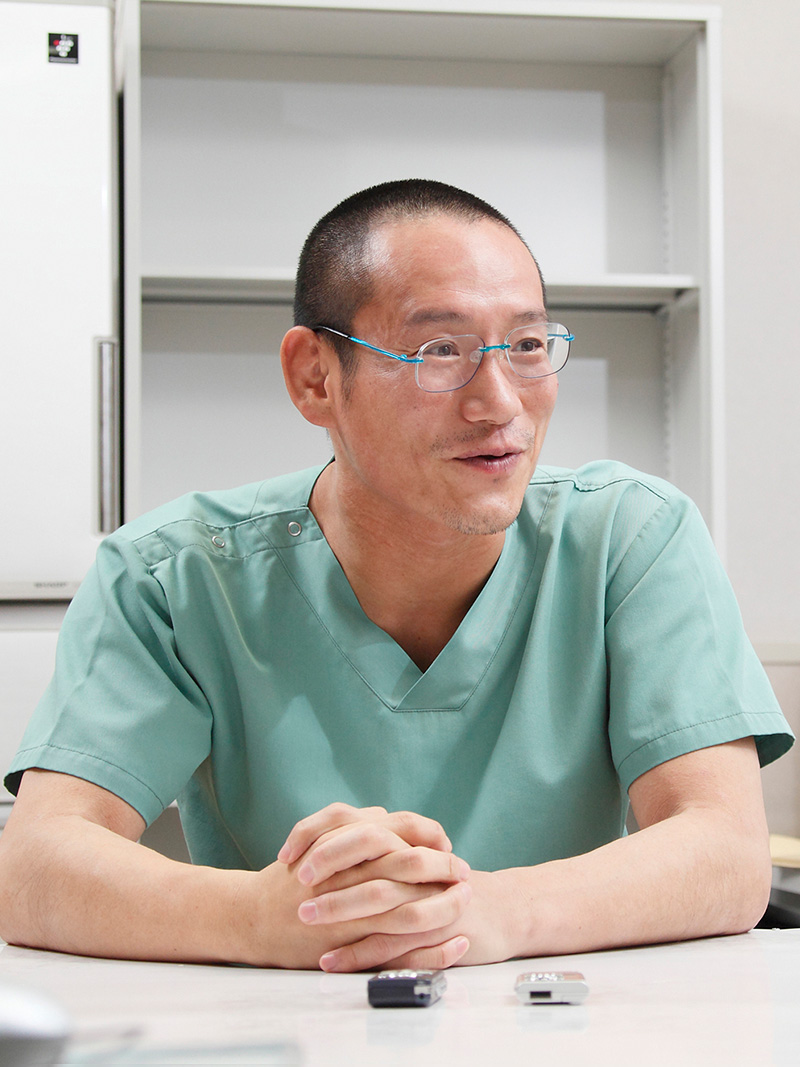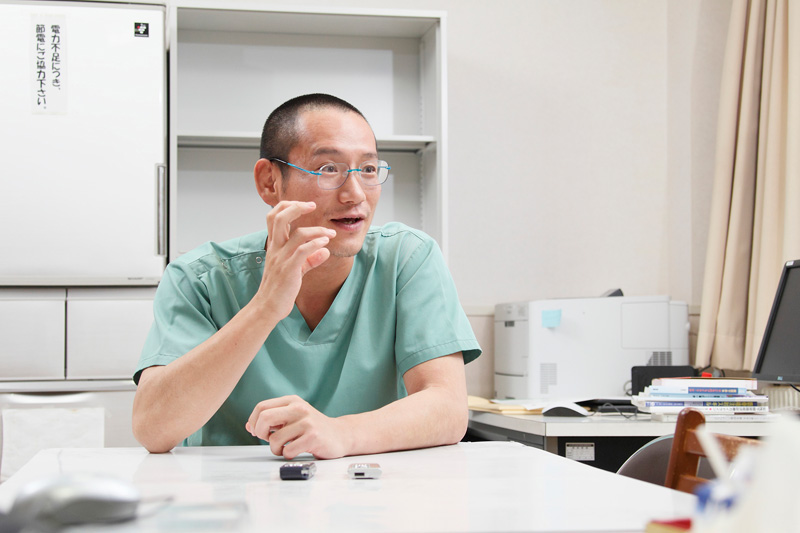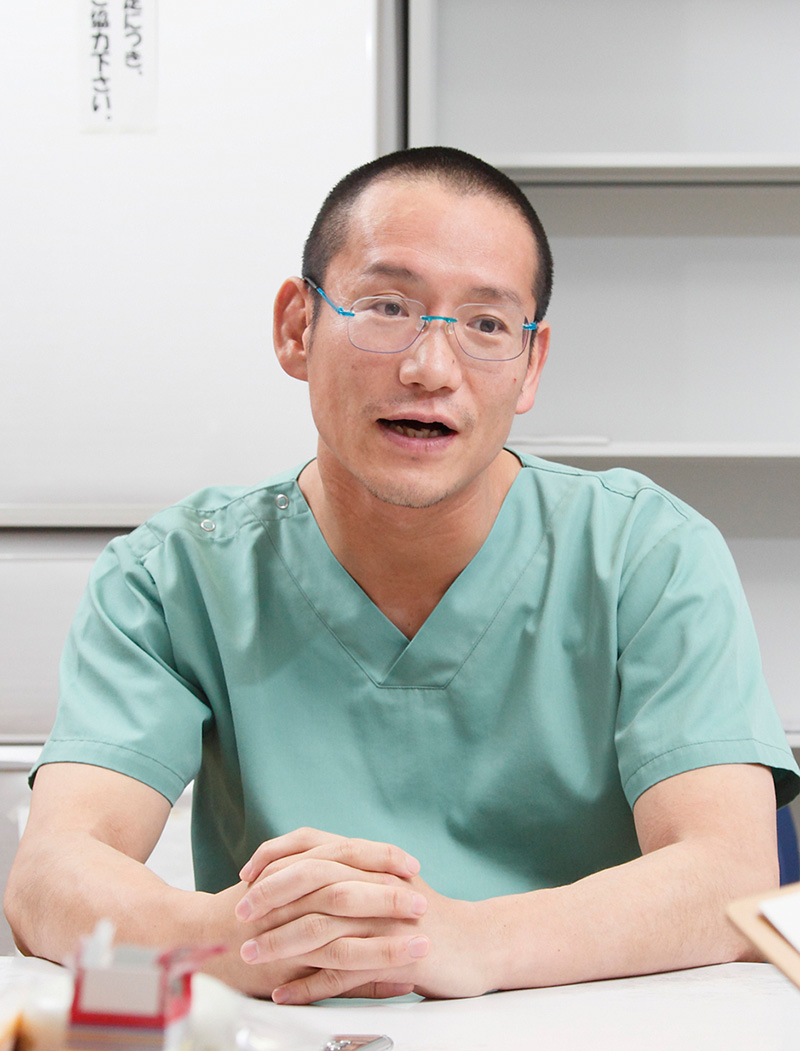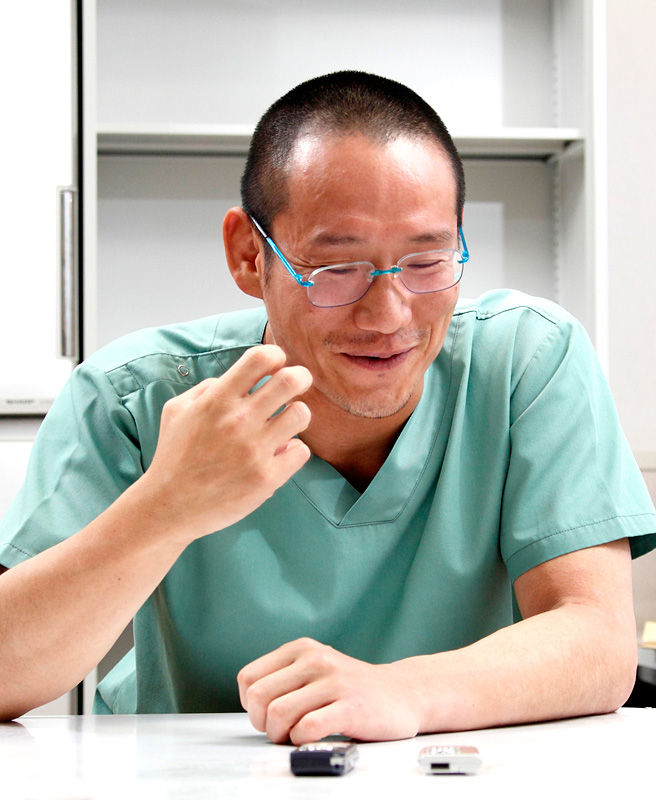ボクシングにのめり込んだ医学生時代
──川島先生といえば、京都大学医学部出身の元プロボクサーの医師という異色の経歴も大きな話題になりました。そもそもなぜ医師になったのですか?
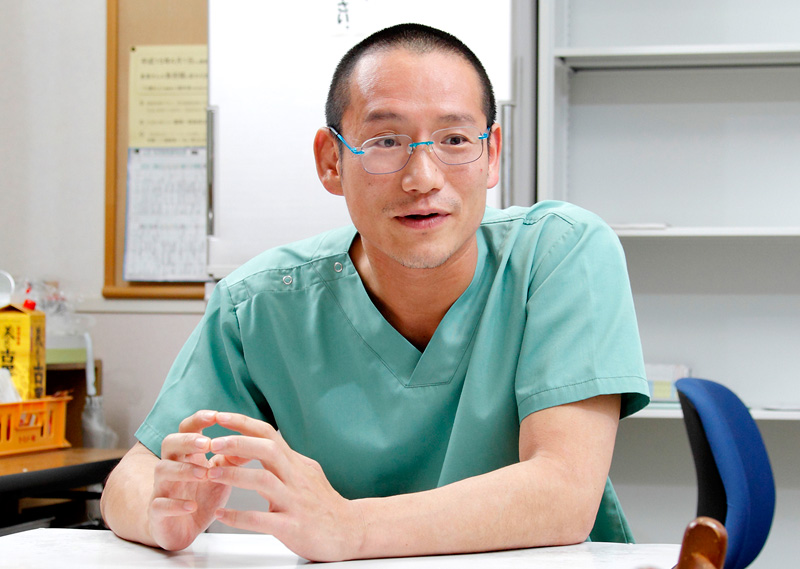
僕はそもそも医者になりたいとは思っていなかったんです。通っていた奈良の高校が進学校で成績がよかったので、両親と学校の先生から医学部へ行けと勧められ、どうせなら一番難しい大学に挑戦しようと京都大学の医学部を受験したところ、現役で合格してしまったんです。
ボクシングも京大に入ってから始めました。中学・高校ではバレーボール部に所属していて、全国大会に出るほどの強豪チームだったのですが、進学校なので高2になると受験勉強のために主要メンバーが次々と抜けていくんですね。だから大学に入ったら絶対に個人競技をやろうと心に決めていました。ボクシングを選んだのは、中高のとき辰吉丈一郎選手の全盛期でよく試合を見に行ったりしていて、そもそもボクシングに興味があったんです。それと中高のバレー部で一緒だった友人がボクシング部に入るというので僕もと入部したというわけです。
──初めて経験するボクシングはどうでしたか?
それまで人を殴ったことなんてなかったのですが、とても楽しかったですよ。ストイックなところが性に合ったということもあってか、すぐにボクシングの魅力に取り付かれました。特定の顧問やコーチもいなくて、自分たちで『あしたのジョー』や『はじめの一歩』を参考にして練習メニューを考えて実践するという自由な感じでした。その代わり、ボクシング部の練習場のすぐ近くに住んでいた、京都拳闘会出身の元日本チャンピオンがときどき教えにきてくれていました。彼の指導で段々と強くなっていくのが実感としてわかり、ますますボクシングにのめり込んでいきました。
罪悪感に苛まれた
──医学部での勉強はどうだったのですか?

そちらは段々苦しくなっていきました。先程お話したとおり、そもそも医者になりたくて医学部に入ったわけではないので、特に病院での実習が苦痛で。自分のような人間がこんな人の命に関わる現場にいていいはずがないと、罪悪感に苛まれていました。
さらに5年生になると勉強や実習で忙しくなってきてボクシングから離れざるを得なかったのですが、中断した途端に体調も悪くなっていました。そんなとき、京都拳闘会からスパーリングパートナーに来てくれへんかと頼まれて、ランニングからトレーニングを再開したとたんに気持ちも晴れたし体調もごっついよくなったんです。やっぱり自分は一生走らなあかんのやと思いました。ちなみに今でも毎日5時半に起きて最低5キロは走っています。
在学中にプロデビュー
──なぜプロボクサーの道を選んだのですか?
6年生になって京大の医局の外科や内科などのいろいろな科に実習のため回るようになりました。いわば就職活動で、気の合う先輩がいる科に就職するんだろうなと思っていたのですが、ちょうどボクシングの本当のおもしろさがわかってきたところでもあり、どっちを取るかすごく悩みました。確かに将来の生活のことを考えれば医者は一生食いっぱぐれることはありませんが、プロボクサーは日本チャンピオンクラスでもまともに食べていけません。でも一方で、医者には後でもなれるけど、ボクシングは今しかできないという思いもありました。悩んでいた時、京都拳闘会のジムで汗を飛び散らせながらボクシングのトレーニングに打ち込む先輩を見て、やっぱり僕の進むべき道はこっちだとプロテストを受け、合格、在学中にプロデビューしたんです。
──当時は本気でプロボクサーとして生きていく覚悟だったのですか?
もちろんです。当時は本気で世界チャンピオンを目指していました。そう思っていないと厳しいプロの世界ではやっていけないんですよ。医学部を卒業した後もどこの医局の科にも就職せずにボクシングに打ち込みました。ただ、せっかく医学部を卒業したので医師免許だけは取っておこうと思い、ボクシングをやりながら試験勉強は続け、26歳のときに3回目の挑戦で医師免許の国家試験に合格しました。同じ年、ウェルター級の西日本新人王とMVPを獲得することができました。
<$MTPageSeparator$>29歳でボクサーを引退
──順調な滑り出しですね。ファイトマネーで生活できていたのですか?

プロデビューして2~3年くらいまでは勝つことの方が多かったのですが、それでもボクシングのファイトマネーで稼げるのは年間100万円程度。しかもファイトマネーって現金でもらえるんじゃなくて自分の試合のチケットを売った分が収入になるんです。だから知り合いの知り合いのそのまた知り合いまで、とにかくツテを頼りまくって必死に売りました。僕は営業がうまかったせいかいつも自分のノルマはすぐ売り切れていつもジムから追加でチケットをもらって売ってました(笑)。それでも年収100万程度ですからね。しかも大学を卒業してすぐ結婚して子どもも生まれていたので、生活は楽ではなかったですね。生活費の大半は薬剤師の妻が稼いでくれていました。日中は子守りをして、夕方仕事から戻った妻に子どもを預けてジムに行くという生活でした。
ただ、その後負けが込んでくると、さらに経済的に苦しくなってきて、30歳の大台が見えてきたとき、このままでいいのかと迷いが生じました。ちょうどその頃家計を支えていた妻が2人目の子どもを妊娠して産休に入り、収入の道が絶たれて来月払う家賃もないという状況になったとき、これはもうたいがいにせなあかんなと。また負けた鬱憤を知らず知らずのうちに家族にぶつけていることに気づいたことも、辞めどきだなと感じた大きな理由ですね。それで2003年、29歳のとき初の10回戦で1ラウンドKOで負けたとき、引退を決意したんです。プロ通算戦歴は15戦9勝(5KO)5敗1分でした。アマで5年、プロで5年のボクシング生活はとても充実していて幸せな日々でした。ボクシングを通して身につけた体力と精神力はその後の人生にも大いに役に立ちましたしね。
和歌山で自給自足の生活
──ボクサーを辞めた後は医師になろうと思っていたのですか?
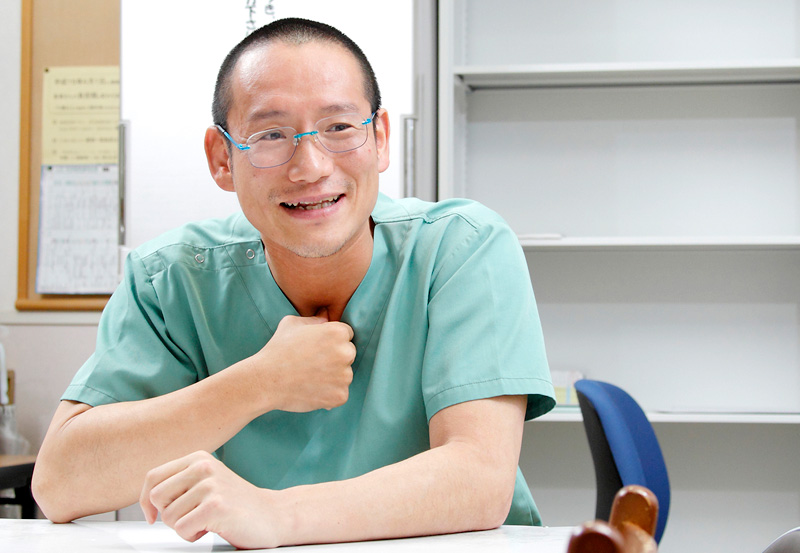
いえ、医者になるつもりはありませんでした。それよりも自分の食べるものは自分で作る自給自足の田舎生活にあこがれて、知人を頼って和歌山の田舎に家族で移住したんです。仕事の方も、医者ボクサーとして有名だったのでまともに医者としての修行を積んだことのない僕のような人間でも先生と呼ばれ、老人ホームや精神病院の仕事をすぐ紹介してもらえて、ボクサー時代よりも稼げるようになりました。
田んぼも無事借りることができてすごくいい感じで望んでいた田舎暮らしをスタートさせたんですが、2年くらい経った頃、行き詰まってきました。まともに医療行為ができないのに医者として尊敬されて働くことがつらくなってきたんです。当時僕が医者としてやっていたことといえば患者さんの身の上話を聞いて葛根湯を処方するだけ。急病人が出たら救急車を呼ぶようなダメな医者だったので、もっと修行を積んでまともな医者になりたいと思うようになったんです。ちょうどそんなとき、京都の漢方病院の院長から誘われたので、家族で京都に戻ってその病院で働くことにしました。
京都の病院で漢方を学ぶ
院長は格闘技好きで、さらにボクシングも再開できたので、最初のうちはやっぱり京都に戻ってよかったと思いました。でもやっぱり漢方の病院なので、1年ほど働くうちに漢方のことはある程度わかるようになったのですが、いわゆる近代的な西洋医学の知識や技術はまったく身につきませんでした。これでは和歌山の田舎から出てきた意味がないな、医療の世界で生きていくにはこのままではダメだなと思っていたところ、京大ボクシング部の先輩で沖縄の徳洲会の救急病院に勤めている医者から「今どうしてんねん」と連絡がありました。現状を話して悩んでいることを伝えると、それなら医者としての修行ができるからうちの病院に来ないかと誘われました。まさに渡りに船という感じでその病院に転職することに決め、まずは僕一人で単身赴任して、後から家族を呼び寄せたんです。
<$MTPageSeparator$>初めて医師としての本格的な修行を積む
──沖縄の病院での仕事は?

この沖縄の病院でやっと本格的な医者としての修行ができるようになりました。でも仕事場は戦場のようでした。24時間稼働の救急病院なので外来の待合室は昼夜問わず患者さんであふれかえっていたし、深夜でも明け方でもおかまいなしに急患を乗せた救急車がばんばん入ってきて次から次へと重篤な患者さんが運ばれてくる。手術室も病室も常に満室という状態でした。そこら中、血の海になってたり、人が死ぬのが当たり前の状況。突然愛する人を亡くして泣き叫ぶ家族の声が響き渡るような職場だったので、つらくて逃げ出したいと思うこともしょっちゅうでした。それでも何とか耐えつつ、1000人、2000人と診察する間に、新しい職場にも慣れたし、できることも一つひとつ増えていきました。
──そんなつらい状況になぜ耐えられたのですか?
やはり、ボクシングを辞めて最初に移住した和歌山の田舎で、医者としてたくさん給料をもらいながら患者さんに何もできなくて悔しい思いをした経験が大きいですね。ここで医者としての知識と技術を身につけて、今度僻地医療に携わるときはちゃんとした医療を提供できるようになりたいという思いで踏ん張っていました。
ただ、仕事は激務でした。先ほどお話したような戦場のような職場だったので、特に最初のうちは仕事の要領もわからへんので家になかなか帰れないんですよね。目の前に死にかけている人がたくさんいるから仕事は無限にあって、どこで区切ったらええのかわからないわけです。だから子どもたちが起きている時間にはなかなか自宅におることができませんでした。それでも久しぶりに時間が取れて子どもたちとたっぷり遊んだ日の翌朝、病院へ向かうため自宅を出ようとしたとき、当時2歳半の長男に「また来てね!」と言われてしまったんです。これはかなりショックでしたね。僕が仕事をするのは家族のためなので、その家族をここまでないがしろにしていては本末転倒やなと思ったんです。また、この病院で医者としてひと通りのことはやれる自信がついたので、ちょうど2年がたつ頃に沖縄の病院を離れることにしたんです。
山形の病院へ
──その後はどうしたのですか?

山形県庄内町にある同じ系列の病院に声をかけてもらいました。この病院は救急病院とは違って、少しのんびりした医療を展開していた点と、田んぼのある環境で子どもを育てられる点が気に入って異動することにしたんです。ここでは総合診療科のNo.2という責任の大きな職責に就きました。
この病院は外科、消化器外科、消化器内科、循環器内科、心臓血管外科以外の専門医がいなかったので、これらの科で診られない患者はすべて診るというポジションで、循環型のシステムを整備しました。特に力を入れたのは小児医療と高齢者の在宅医療です。
──循環型のシステムとは?
例えば、消化器外科の場合は胃腸関連しか診療しないので、胃の手術が終わったら医療サービスがそこで途切れてしまいます。しかし僕らは救急車で病院に運ばれてきた患者を救急外来で診断、初期治療をして、各専門科が得意でない症例は全て自分たちの病棟で診療します。お年寄りの患者さんの多くはその後自宅に帰っても熱を出したりして救急車でまた病院に帰ってくることになるので、そういうことのないように、患者さんの急性期の治療が終わって家に帰った後も在宅医療で手助けします。とにかく途切れずに患者さんを診るという継続的な医療サービスを確立したわけです。
仕事以外の部分では、病院の近くに田んぼを借りたのですが、お年寄りの患者さんたちに稲作の技術や歴史、精神などさまざまなことを教わりました。僕の子どもたちも地域の皆さんに育ててもらいました。この頃は稲作と子育てを通じて地域に溶け込み、医療という仕事で地域に恩返しをするというライフスタイルを確立し、久々に自分の生活にやり甲斐と手応えを感じ始めていました。
しかし、庄内に来て3年目、半年間の研修のために自宅から20キロ離れた病院へ通わなければならなくなりました。庄内での生活を手放したくなかったので「半年も職場を離れたくない」と上司に訴えたのですが、研修を終えれば総合診療医という資格が取れるから辛抱しなさいと強く勧められたのでしぶしぶ承諾して通い始めました。そんなときに東日本大震災が起こって、医療ボランティアで本吉病院に入り、そのまま院長になったというわけです。(※本吉病院での活動については前編を参照)

本吉病院のスタッフと一緒に
上善如水
──そしてこれからは地元である奈良に戻って新しい生活を始めるというわけですね。しかし京都→和歌山→京都→沖縄→山形→宮城といろいろな土地を転々としていますが、ひとつのところに長く留まりたくないのでしょうか。
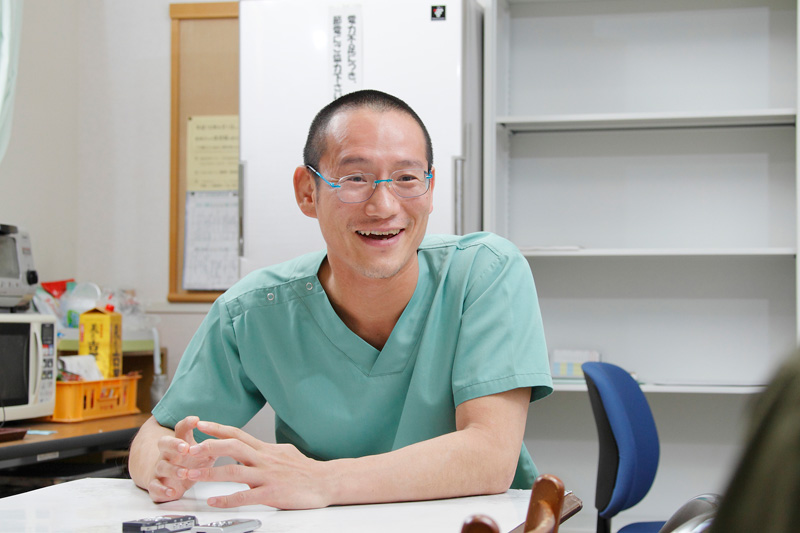
「上善如水」といいますか、僕には常に流れていたいという欲求があるようです。同じ場所に長くいたら慣れて楽ができますが、環境が変わると仕事も生活も苦労するので、それが修行になります。修行僧のことを雲水といいますが、そういうニュアンスなのかなと自分では思っています。
──ご家族はどう感じているのでしょう。
どこにも3年以上いてないですからね。家族もよく僕のわがままについてきてくれたと思いますよ。僕はこれまで何回も死んでもおかしくない事故に遭ってますが、僕が死んだ方が家族は幸せなんとちゃうかと思うときがあるんですよね。僕と一緒だと絶対平穏無事には暮らせないですからね。娘も家を出て行くくらいですから。
──奥さんの忍耐力もすごいですよね。
これまで4人の子育て含めて家事の一切を妻に任せてきたので、妻が倒れる前に病院を辞められてよかったなと思っています。医師という職業は、困っている人を助けて感謝されるし、給料もそこそこもらえるので、やりがいあるしおもろいんですよね。ただ、病院によってはそれこそ家に帰る暇もないくらい忙しいので、そこでバランス崩れると生活が成り立たなくなるんですよね。
妻のことを結婚したころは調子に乗って「うちの嫁が」とか言っていたんですが、あるとき妻の方がお上やなと思って「かみさん」と言い方を変えたんです。本吉に来てからは神様だなと思って手を合わせてます(笑)。
医師という仕事のやりがい
──具体的に仕事のやりがいはどんなところにありますか?

在宅医療に関していえば、家で亡くなってよかったねと言えるときが一番やりがいを感じますね。それは本人も家族も幸せでしょうから。あとは、地域医療に携わっていると、その地域に住んでるほとんどの人と知り合いになれるので、道を歩いているときも居酒屋で飲んでいるときもみんな僕に声をかけてくれるときにこの仕事をしていてよかったなと感じますね。
僕はそもそもの性分として困った人の相談に乗るのが好きなんですよ。今後も医療に携わるとしたら予防、つまり病気を治すというよりは、いかに健康を維持するかということに関わりたいですね。また、病気の問題は地域の問題とも直結しているので、街づくりにも興味関心があります。それから今後の地域医療を担っていく若手医師の育成にも力を入れてきました。
理想の医療とは
──長年地域医療に携わってきた川島さんの考える理想の医療とはどんなものでしょう?

各地の医療機関や教育機関などからの依頼で講演をすることも多い
医療が偉そうな顔をしてたらあかんと思うんですよ。各市民が自己管理をして医者なんかにかかったら終わりやという自覚をもっていただいて、どうしようもないときに仕方ないから相談しに行くというのが医者であるべきだと思っています。
地域医療について講演で話すとき、よくサッカーにたとえています。フォワードはワクチンや保険や教育。これらが直接点を取る選手たちです。中盤の一番運動量の多いミッドフィルダー役が、なるべく歩きましょうとか塩分の少ない食事を摂りましょうとか歯磨きや早寝早起きなどの規則正しい生活をしましょうといったヘルスプロモーション。ゴール前のディフェンダーは福祉や介護。最後の砦のゴールキーパーが医療なんです。サッカーでもゴールキーパーが獅子奮迅の活躍をするのは負け試合なので、そこまでいかに患者を来させないか、つまり「予防」が重要なんです。僕は名前がちょうど日本代表のゴールキーパーと同じ川島なのでこの話はけっこうウケます(笑)。
何のために働くか
──川島さんは何のために働きますか?

お金のためです。それはイコール家族を養うため。今、子どもが4人いますが、彼らを食わせたり教育を受けさせたりしなきゃいけないですからね。本当はもっとお金をかけるよりも手をかけたいと思ってるんですけどね。医者をやってると、そのへんのバランスが難しいです。
──今後の夢や目標は?
今後のことはまったくわからないです。10年後どころか来年自分が何をやってるか全然読めません。逆に読めたらつまらないなとも思います。ただ、ここのところずっと地域医療に取り組んでいるのでそれは続けたいなと思ってます。