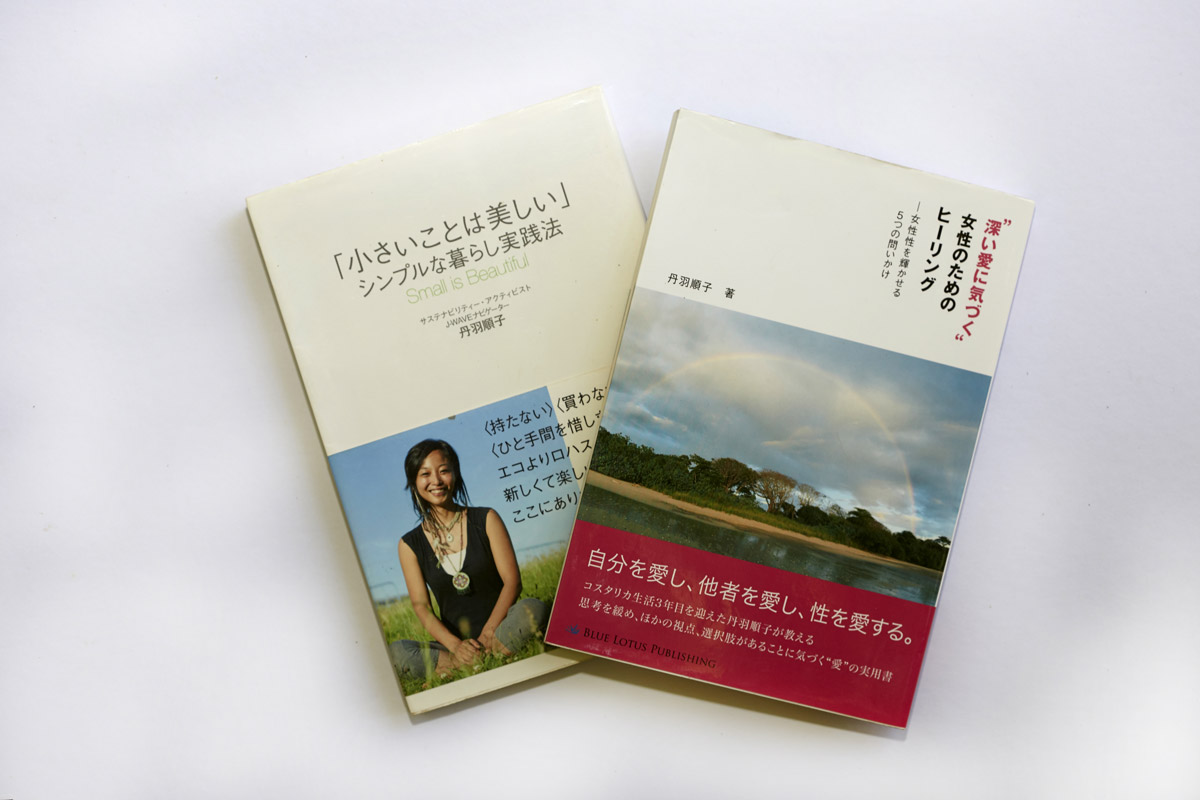子どもの頃から海外志向が強かった
──現在コスタリカにお住まいですが、幼少期から海外の文化に触れる機会も多かったのですか?

父親の仕事の関係で、2年ほどアメリカ東海岸のバージニア州に住んでいました。また、祖父母も英語の先生で、両親も英語の教授を務めていたので、インターナショナルな要素は少なからずありましたね。自分自身の性格もあるのでしょうが、将来は日本でずっと暮らすイメージはあまりもってなかったです。中学高校はいわゆるお嬢様学校に通っていたのですが、私自身はずっとバレー部で体育会系のタイプでした。チームメイトとも仲がよくて何の不満もなかったのですが、やっぱりこのまま高校時代終わっちゃうのはもったいないと思って、高2のときに1年間アメリカに留学もしていました。
──大学進学後は、どのような勉強や活動をされてきたのですか。
大学時代は環境系の先生の秘書のようなバイトをやっていました。そもそも環境系に興味があったわけではなくたまたま高校の先輩がバイトをしていて、やってみないかと誘われたんです。時給もいいし、たまに国際会議にも連れて行ってくれるから、おもしろそうだと思って。後にその先生のご縁でイギリスの大学院に行くことになったので人の縁でおもしろいと思いますよね。大学卒業後はNHKに就職しました。
NHKに入社も3年で退職
──志望動機は? 学生の頃からマスコミに興味があったのですか?
いえいえ。アメリカには住んだことがあったものの、私はあまり日本の他の場所へ行ったことなかったので、国内転勤のある仕事がよかったんですよ。NHKだったらどこか地方に配属してくれるのでは、という期待がありました。海外の支局に行きたかったというよりも、日本の田舎に行きたかったんです。それで入社後は自ら希望して奈良支局に配属となりました。でも3年で辞めちゃったんですけどね(笑)。
──せっかく難関を突破して入社したのになぜですか? 退社を決断するまでに至った経緯を教えてください。

今でこそ、個人で動画配信するのは一般的になりましたが、当時はまだ珍しいことでした。そんな時代に記者として小型のビデオカメラをもたされたことで、これからは個人が配信していく時代だなというのを感じたことが1つ。
もう1つは、ドキュメンタリー映画監督の森達也さんが撮られた『A』という映画を観たことです。こちらの方が理由としては大きいですね。その『A』には私と同じNHKの記者がオウムの方にインタビューしているシーンがありました。記者側がなんとかいいコメントを引き出そうとしているのですが、それをオウムの信者の方が「君とは話してる言葉が違うんだよ」と言って、記者が言葉に詰まってしまうんです。これは、まさに私でもそうだろうなと思いましたし、マスメディアにいたらこうなると思っちゃったんですよね。それでNHKを辞めたんです。
その後、森さんのところに押しかけ、「一緒に映画を作らせてください」と直談判して一緒に映画を作るようになったんです。映画としては最終的に形にはならなかったのですが、今でも森さんは兄貴分のような存在ですね。また、私がその後に結婚する予定だったことも退社の理由のひとつにありました。
<$MTPageSeparator$>環境問題を学ぶため、イギリスの大学院へ
──そこから独立されてフリーとして活動を始められたのですか?

そうですね。ドキュメンタリストとして活動しながら、森さん繋がりで知り合った、『A』のプロデューサーでもある安岡卓治さんの紹介で、日本映画学校の講師やったりもしていました。映画を作ったこともないのに(笑)。そして、だんだん「もっと世界に出たい」「いろいろなことを経験したい」という気持ちが強くなり、1年ぐらい家に帰らなかったりしていました。結婚しているのにひどい話ですよね。その後、離婚をして、イギリスの大学院に留学することにしたんです。
──それが先ほどのお話のバイトをしていた大学の先生の縁だったのですね。どんなことを学びたくて留学されたのでしょうか。
その頃、もう少し仕事の軸をしっかり立てなきゃいけないと思っていました。そんな中、いろいろな分野で環境問題が取り沙汰されるようになり、関心をもっていたら、その先生が「奨学金も出るみたいだからトライしてみる?」って大学院のプログラムを薦めてくれたんです。そして試験に無事合格し、30歳の時にイギリスに渡って、環境問題について学ぶことになりました。
サスティナブルとリーダーシップを学ぶ
──具体的にはどのようなことを専攻されていたのでしょうか。
ひとくちに環境問題といってもすごく広いじゃないですか。私は、生物学や科学的なことということよりも、持続可能な社会にするために、企業や地域、NPOや学校で何をするかという「サステナビリティ」と「リーダーシップ」を学びました。日本とイギリスの両方の企業、行政、NPOでインターンを経験し、最後にジュネーブにある国連組織でインターンをして終了というコースでした。だから座学じゃなくてかなり実践的なプログラムだったんです。この1年の留学で、大学を出ているのに世界がどんなふうに動いているのか全くわかっていなかったことを痛感しましたね。あのプログラムに参加できたのは本当にラッキーなことでした。
帰国後はドキュメンタリー映像の制作などを行っていました。でも帰国したばかりのころは、焦っていた面もあったかもしれません。どんどん悪化する地球環境に対して何もできてない自分に対してジレンマを抱えていて。周りにも自分の考えを押し付けるような、うっとおしい人だったと思います(笑)。それでも「よし、これから頑張っていくぞ!」と気合いが入っていたその矢先に、妊娠したんですよ。出産した時、人生観、価値観などが一変しました。
もう何も作り出さなくていい
──具体的にはどのように変わったのですか?

自分の身体から新しい命を産み出すって、これ以上クリエイティブなことはないですよね。だからもうすべて満たされてしまって、これまでは割と攻めるタイプの人生を送ってきたのに、上昇志向とかなくなりましたよね。もう何もクリエイトしなくてもいいというか、もう何かしなくちゃとか、誰かに評価されなきゃといった気持ちもきれいさっぱり消えて、何もなくても幸せを感じるようになりました。
そして、出産を機に鎌倉を拠点にして地域活動を始めるようになったんです。
──鎌倉を選んだ理由はなんですか。
海も緑もあって、東京にも近いから仕事もしやすいので、縁もゆかりもなかったものの、鎌倉ならのんびり子育てできるのではと思ったからです。
──鎌倉で子育てをしながら留学時代に学んだ内容を実現しようという気持ちだったのでしょうか。
いえ、鎌倉では子育てに専念しようと決めました。これまではずっと何かを求めて走ってきていたので、ここで立ち止まる時なのかなと思ったんです。そこで、同じように身の丈に合った暮らしを地域コミュニティでつながり合って作っていくことにしました。「かまわ」というNPOを仲間うちで立ち上げたんです。
──「かまわ」ではどのような活動を?
「鎌倉無銭旅行」といって、全部物々交換で成り立たせる企画を行いました。たとえば、カフェでご飯を食べた時、皿洗いをしたら無料になる、といったような形です。最初は商店街の人たちも、商売に影響を及ぼすと言って反対していたのですが、だんだんノッてくれて。お店同士の交流が生まれたり、お金の価値を考えさせられた、という声もありました。ブログに書いて発信していると、「うちの媒体で連載してください」と声がかかったり、エコイベントの司会の依頼が舞い込んだり。そんな仕事をしながら子育てをしていました。
また、自分では「xChange(エクスチェンジ)」という、ファッションアイテムに特化したフリースタイルの物々交換会を始めました。これは完全に思いつきで始めたものだったんですよ。普段から、地域のお母さんたちは子育てに忙しくてあまり買い物にも行けないことに悩んでいました。自分で洋服を作ろうと思っても、環境にどれだけの負荷がかかるのかというのは大学院時代によく勉強して知っていましたし。おしゃれをしたいのにどうしたらいいのだろうと思っていました。そんなときにイベントをやるという友達から、「何かイベントで出し物ない?」と相談されたんです。そこで「服の交換会をするのはどう?」と提案して始まったんですよ。やってみたらすごく楽しくて、大盛況だったんですよね。これまで本当にいろいろなことをやってきましたが、私の活動の中で唯一続いてるものです。
でもそんな鎌倉での満たされた生活もある日突然終わりを迎えました。3.11の東日本大震災の発生によって。