外資系コンサルティング会社からスタート
──前編では主にSAFLANの活動についておうかがいしましたが、本業の弁護士としての仕事について教えてください。そもそもどうして弁護士になろうと思ったのですか?

学生の頃から弁護士になりたかったわけではないんですよ。早稲田大学を卒業して最初に務めた会社は現在のアクセンチュア株式会社、当時アンダーセンコンサルティングという経営コンサルティング会社でした。
これも偶然というかなりゆきで、私は大学生のときから最初はどこかの企業に就職してもいずれは独立して働きたいと思っていました。中でも記者やジャーナリストにあこがれていたので、就職活動のときに新聞社や出版社などをいくつか受けたのですが全部落ちたんです。そっちの方面には才能がないのかなと思い就職関係の資料を読んでいたら、あいうえお順で一番最初にあったアンダーセンコンサルティングが目に入りました。当時は経営コンサルティングなんて全くイメージも湧きませんでしたが、何かおもしろそうだなと応募してみたところ、面接官と意気投合して通ってしまったんですね。
私は大学時代、まじめな学生ではありませんでした。授業に出ないで麻雀ばかりやっていたので成績も悪いし、ザック担いでアジアやアフリカをふらふら旅していたら留年もしてしまったので、何が評価されたのか不思議でした(笑)。ただ、そうした経験の中で考えたことを、自分なりの言葉で語ったことが面接官にはおもしろいと映ったのかもしれません。選考の過程で出会った人たちが魅力的だったし、外資系のコンサルティング会社の人は一生勤めるという風土でもないと聞いたので、これもご縁と思って入社したんです。
──入社後はどんな仕事を?
「人」の観点に着目して経営革新を支援するコンサルティングの部署に所属していました。企業が何か変わらなくてはならないというときに、経営戦略や業務のやり方、あるいは情報システムなどさまざまな観点からのアプローチが考えられますが、いずれにしても働くのは「人」ですよね。人事制度や組織の設計、あるいはナレッジと呼ばれるような仕事のコツのようなものを、どうやって組織の共有財産として活用していくかというプロジェクトなどにも取り組みました。大企業同士の合併の際に両社の業務のやり方を統合しながらよりよいものに変えていくにはどうすればよいか、といったプロジェクトもありました。ハードワークな会社だったので、いつも深夜まで働いていましたね。大変でしたがやりがいもありおもしろかったですよ。
早稲田大学法科大学院へ
──ではなぜ辞めて弁護士の道へ?

先ほどもお話した通り、元々独立志向が強く、そう長くは会社にいるつもりはありませんでした。入社5年目くらいのときに30歳を目前にして、さて、どうしようかなと思っていたところ、法科大学院、いわゆるロースクールが創設されることを知り、興味を引かれました。というのも、例えば企業再生のプロジェクトに関わったとき、不良債権処理の現場の最も重要なシーンで弁護士や会計士が力を発揮しているのを目の当たりにしまして、経営コンサルティングに取り組む上での法的な問題解決の重要性を痛感していたからです。
また、世間ではこれまで弁護士は敷居が高いというイメージでしたが、ロースクール教育を通じてもっと庶民の間に法的なサービスを広げていこうという司法制度改革の理念もおもしろいと感じました。自分が弁護士になるかどうかは別としても、法律家を目指す優秀な集団の中で切磋琢磨することは、人脈を広げるという意味で価値があると思ったのです。それで取りあえず法律の世界に飛び込んでみようと、2004年に早稲田大学法科大学院の第一期生として入学しました。入ってみると予想以上におもしろく、のめり込みまして、法科大学院では三年間学び、2007年に修了し、司法試験に合格。一年間の司法修習を経て、2009年から東京駿河台法律事務所という事務所で弁護士として働き始めました。
生の事件に触れて弁護士に
──ビジネスのために法律を学ぶ目的でロースクールに入学したのに弁護士になったのはなぜですか?
ロースクールで色々な人に刺激を受けて、やはり自分が弁護士になりたいと思ったからです。これはロースクールに入学してよかったと思う点なのですが、ロースクールは法曹(法律を扱う専門職として実務に携わる者)を育てる教育機関なので、在学中から実務に触れる機会を与えてくれるんです。臨床法学教育というんですが、実際に現役の弁護士が扱っている生の事件に関わって、学生も一緒に依頼者の方から聞き取りをしたり訴状を作る手伝いをしたりするんです。例えば不当に勾留されていた人を釈放したり、お金を騙し取られて困ってる人にお金を取り返してあげたりすると、依頼者の方はやはりすごく喜ばれるんですね。私自身は学生ですから大したことはやっていないのですが、困っている人を助けることに少しでも関われたことがうれしかった。
このような経験を通じて、弁護士には、目の前の人が困難に直面していて、自分が手を差し伸べなければこの人は死んでしまう、大変な目にあってしまうという局面があるということを実体験として知りました。そこで弁護士っておもしろいなと思ったんです。これが弁護士になりたいと思った直接のきっかけであり、今振り返ると大きな転機ですね。
いきなり貧困問題に取り組む
──弁護士になってからは主にどのような分野を?

弁護士登録をしたのが2008年の末ころで、就職先の東京駿河台法律事務所には年明けの1月6日から勤務することになっていました。それまでの2週間ほどはやることもなく、正月にテレビで箱根駅伝を見てたんですね。そのとき、緊急速報のテロップが流れました。前年に起こったリーマンショックの影響で大手メーカーなどから解雇されたたくさんの派遣労働者が日比谷公園に集まっていて、支援するボランティアがテントを設営して政府と交渉をしているというニュースでした。当時大きな話題となった派遣村です。
日比谷公園は司法修習で1年間通った東京地裁の目の前だし、気になったので現地に見に行ったんです。もう弁護士資格はあるわけだし、何かできることもあるだろうと。その流れで巻き込まれるように活動に参加することになりました。派遣村の村長をしていた「NPO法人 自立生活サポートセンター もやい」の代表(当時)の湯浅誠さんとは、その後も何かと一緒に活動しています。
私が実際に担当したのは、解雇されて住む家もお金もない大勢の派遣労働者の方々を一人ひとり福祉につなげるお手伝いをする仕事でした。彼らと一緒に役所に行って生活保護申請をし、ちゃんと生活保護費を受給できるように役所の担当者に意見書を提出したりして交渉するんです。弁護士といっても新人でズブの素人です。先輩弁護士のやり方を見ながら、六法全書と生活保護手帳を携えて現場で必死に考えました。それが私の弁護士としての初めての仕事になったんです。
このとき集まっていたボランティアの人たちと知り合いになり、その後、東京の山谷で無料法律相談を実施するなどホームレスや生活困窮者の支援活動に関わるようになりました。2013年からは山谷に集まる生活困窮者の支援団体である「NPO法人 山友会」の理事も務めています。
<$MTPageSeparator$>高校生のころの原体験
──SAFLANにしても生活困窮者支援にしても、そもそも河﨑さんは目の前に困ってる人や苦しんでいる人がいれば放っておけないという気持ちが強いのでしょうね。
みんなそうだと思いますよ。特別私が善意にあふれているわけじゃなくて。

──でも困ってる人の力になりたいと思っても実際に行動に移せない人もいるじゃないですか。もっと若いころからそういう気持ちがあったわけではないのですか?
そう言われて思い出してみればいくつか原体験みたいなのがあります。1つは高校生のときに、O君という友人と駅のホームを歩いていたときに、後ろの方でドスンと大きな音がしました。振り向いたらお婆さんが階段から転げ落ちていました。あまりの突然のことにびっくりして私は動けなかったのですが、彼はいち早く駆けつけて「大丈夫ですか」と声をかけ、駅員さんに連絡して対処したんですね。
もう1つ、同じくO君とショッピングセンターのアイスクリーム屋で受験勉強をサボって話をしていたときのことです。隣のテーブルにすごく体格のいい強面の父親とおとなしそうな母親と4~5歳くらいの男の子の家族連れが座りました。男の子が父親に何かを言ったとき、父親が思いっきりその子を殴り、その子は吹っ飛んで柱に頭をぶつけて泣き出しました。母親は顔をそむけています。いわゆるDV家庭でした。そのときも私は何が起きたんだろうとびっくりして動けなかったのですが、O君がすぐに立ち上がって「子どもに何をしてんだ!」とその父親に抗議したんです。見るとO君自身も涙を流してるんですよ。悔しかったんでしょうね。今思い出しても涙ぐんてしまうんですが、あのとき彼は立派だったなあと思いますね。
2つとも20年以上前の何気ない思い出なのですが、あいつは動けて俺は動けなかったなと思ったことを今でも覚えています。先にお話した阪神大震災も含めて(※前編参照)、こういった何かが起こった現場で自分自身は何もできなくて悔しい思いをしたという経験が自分の中にいくつかあって、だからできるときは何かをしないといけない、そしてそういうことができる立場になりたいと思ったことも最終的に弁護士という仕事を選んだ動機の1つとしてあるんじゃないかと思いますね。
弁護士の本能

そもそも弁護士という職業は目の前の困っている人のために取れる手段が多いし、それが社会から期待されている役割だからそうしているだけだと思いますね。医師なら目の前にケガや病気で苦しんでいる人がいれば本能的に治療しようとするでしょう。それと同じことなんですよ。
もちろん事務所を維持し、生活をしていくためには一定の収入が必要です。その、何とか生活していける程度の経営基盤を得られているのは、アクセンチュア時代にコンサルタントの仕事を通じて経営の基本的な知識を身につけていたことが大きいかもしれません。当時の人脈でいまだに仕事を紹介してくれる方が多いのも助かっています。
独立して法律事務所を立ち上げる
──最初に入った東京駿河台法律事務所では他にどんな仕事を?
もちろん生活困窮者支援だけをやっていたわけではなく、企業の経営相談全般、民事、刑事、家事などなんでも取り組みました。約4年間弁護士としての修行を積んだ後、同世代のこれはと思う弁護士に声を掛けて、2013年3月、現在の早稲田リーガルコモンズ法律事務所を設立したんです。
──なぜ自分たちで事務所を設立したいと?

東京駿河台法律事務所もすごくいい事務所だったのですが、自分たちで好きなようにゼロから新しい事務所を作り上げたいという気持ちが強かったんです。多分性格的に何でも1から自分でやってみたいんですね。今回取材いただいたこのスペースも、コモンズスペースと名付けていますが、リラックスできる空間になっているのではないかと思います。通常の法律事務所にはこういうものは作らないと思うんですが、例えばデザイン事務所とかスタートアップ企業なんかだったら珍しくないですよね。法律事務所という枠を取っ払って、事務所を設計してみたかったんです。それと、社会に対して何か新しい物事を発信していくための基地のようなものを作りたかったというのもあります。
──なぜ九段下にあるのに「早稲田リーガルコモンズ法律事務所」という名称なのですか?

早稲田ロースクールと提携関係にある法律事務所だからです。私や事務所設立メンバーの多くは早稲田ロースクールの一期生だったので、弁護士になった後も、後輩の指導をしたりと、早稲田ロースクールと良好な関係を続けていました。早稲田ロースクールで教授をしていた遠藤賢治教授が退任するにあたり、弁護士登録をして、後進の指導のための事務所を作りたいと話しているのを知り、私たちの世代のメンバーがそれに合流する形で、早稲田ロースクールの実務教育に協力する法律事務所として立ち上がった。それがこの事務所の発祥の経緯なんです。
なお、「コモンズ」というのは共有財、入会地などといった意味で、誰のものでもなく、みんなのもの、受け継がれていく価値、という意味合いをもっています。私たちがロースクールで学ばせてもらった先人の知恵やリーガルスキルを、次の世代に伝えていくための基盤のようなものを作れたら、という事務所設立の理念を込めてこのように名づけました。
<$MTPageSeparator$>弁護士事務所の代表として

早稲田リーガルコモンズ法律事務所のメンバーのみなさん
──弁護士事務所の代表としてはどのような仕事・役割があるのですか?
当事務所は複数の弁護士による共同経営で成り立っており、現在は私ともう1人の代表パートナー(前述の遠藤賢治弁護士)を含め16人のパートナーと2人のカウンセル、7人のアソシエイト、合わせて25名の弁護士が所属しています。パートナーは事務所を経営していくためのお金を出している出資者であり、経営の方向性について決定権をもっている共同経営者という位置づけです。それぞれ自分のクライアントをもっており、報酬も自分が働いた分だけ得ることができます。アソシエイトは経費負担のない弁護士で、主に弁護士経験2年以下の新人です。毎年早稲田ロースクールを修了して司法試験に合格した新人を数名採用しています。アソシエイトの所属期間は2年間で、その間に実力をつけて独立するなり、他の事務所に移るなり、次のステップへ進んでもらうということになります。
当事務所は個人事業主の集まりのような感じで、いわゆる一般の企業のようにトップに社長がいて、以下副社長、専務、部長、課長......というようなピラミッド型の組織にはなっていません。あえて例えるなら、パートナーがドーナツ状に広がって輪をなしていて、養成対象であるアソシエイトがその輪の真ん中でパートナーに包まれている、という感じでしょうか。極めてフラットな組織だと思います。
ですから私は経営者という立場ですがトップダウンではなく、経営方針など重要な議題は16人のパートナーで議論して決める合議制です。私の代表としての一番大きな役割はその場のコーディネーションですね。
──意見をまとめるのがなかなかたいへんそうですね。
そうなんですよ。最高裁の大法廷でも15人ですからね。16人もいれば当然考え方も多様ですから、合意形成にはどうしても時間がかかります。その辺りの苦労はありますが、花見やバーベキューなど定期的に事務所イベントを開催したり、部活動を推奨したり、お互いリラックスしてコミュニケーションを取れる場を設けるなど人間関係をしっかり作るような努力をしているので、今のところパートナー間で目立った対立があるわけでもなく、スムーズに運営できていると思います。
一弁護士としての仕事
──いわゆる一弁護士としての仕事もしていらっしゃるんですよね。
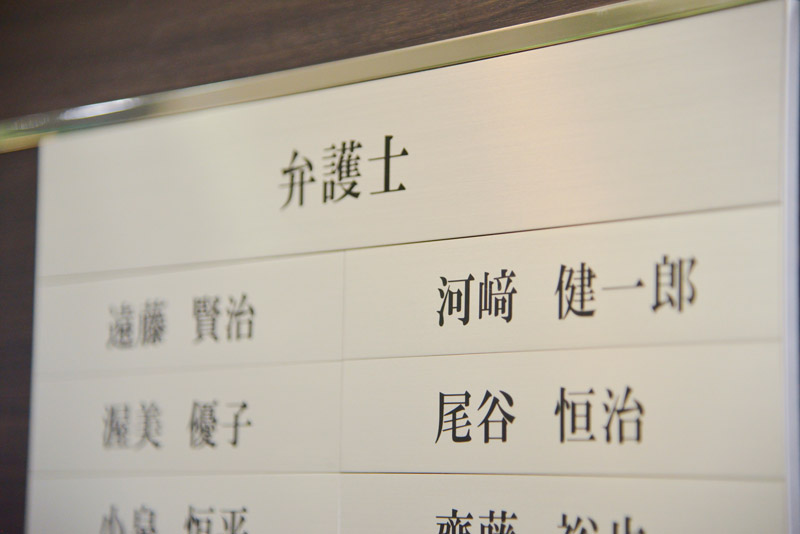
もちろん行っています。中小規模の事業者の方々の経営相談全般、いわゆる顧問弁護士としての仕事が多いのと、あとは相続や離婚、子どもの問題などの家事事件全般を扱うことが多いでしょうか。実際にクライアントと会って相談を受けたり、裁判所の法廷に立ったりもしていますが、事件を他の弁護士と2人で受け持つ共同受任が多いです。私自身が法廷に行くのは週に2~3回程度ですね。
──早稲田リーガルコモンズ法律事務所とSAFLANとは別なのですか?
はい。この事務所とSAFLANは別物です。ただ、SAFLANのメンバーの何名かが当事務所の弁護士で、SAFLAN副代表の福田健治弁護士や、栃木県北地域での集団ADR(代替的紛争解決手続)の団長を務めている尾谷恒治弁護士も当事務所に所属しています。
弁護士としてのモチベーション
──弁護士としての河﨑さんを突き動かしているモチベーションは何なのでしょう。
絶対にこれをやらなければならないという使命感はないんですよ。基本的には、目の前に来た球を打ち返すというスタンスです。この問題はやりすごしてはいけないなと思ったら調べてみて、自分にできることがあれば関わるという感じですね。
先にもお話しましたが、SAFLANの活動に取り組んでいるのもたまたまなんです。そもそも私は環境問題の専門家でもないし原発問題にも全然興味がなかった。もしこの時代に東京にいなかったら、また、幼い子どもがいなかったらここまで入れ込んでいなかったと思います。世の中にはたくさん問題があって、どれを選んでもいいわけですが、いまのテーマに取り組んでいるのはいくつかの偶然と人の縁が重なったからだと思います。
社会全体がこうあるべきという政治的な思想や設計主義的な考えも私の中にはほとんどありません。あるのは自分が親世代から受け継いだよいものをそのままに、悪いものはちょっとだけマシにして次の世代に繋げたいという思いだけなんですよね。だから私は自分を分類するなら「保守」だと思っているんです。周囲からはそう見られていないようですが(笑)。私たちは社会の一員なので社会をよりよい形で子どもたちの世代に伝えていくことは大人の責務だと思うんです。
<$MTPageSeparator$>仕事のやりがい
──では仕事のやりがいはどんなところに感じますか?

何か自分にできることをして、その結果誰かが困っている状態から脱してよりよい状態になって喜んでくれることにやりがいを感じます。医師が治療した人がよくなってうれしいとか、先生が教育した子どもが成長してうれしいというのと同じで、成果がすごくわかりやすいので、自己実現感も得られやすい職業だと思います。
例えば山谷に流れ着いたあるホームレスの方は、私が法律相談を受けた時には、顔は垢で真っ黒、髪もヒゲも伸び放題で本当にボロボロの格好をしていました。それが生活保護を受給できるようになって3ヶ月もすると、髪の毛を切って髭も剃って血色もよくすごくこざっぱりした格好になって、わざわざ私のところに御礼を言いに来てくれました。あまりに様子が変わっているから、言われるまで誰だかわからないということもありました。また、そうやって復活した人が、支援する側に加わってくれることもあるんです。ボロボロの状態から立ち直って人としての尊厳を取り戻すだけでも十分うれしいのに、さらに困窮してる人を支援する側に回ってくれるというのは言葉にならないくらいうれしいことですよね。
また、先日も寒い夜に神保町の脇道で土下座するように倒れこんで固まっている40代半ばくらいの男性を見かけました。思わず声をかけてみると、1週間何も食べず街を放浪しているということでした。いくら日本も格差社会が広がっているといわれていても、行き倒れている人に実際に出くわすことがあるんだと驚きました。取りあえず近くのコンビニに連れて行って、おにぎりなどを買って食べてもらい、同時にもやいや山友会などのホームレス支援の団体に連絡。その日は、私の事務所の前のビジネスホテルに泊めて、翌朝もやいに連れて行って福祉に繋がりました。
こういうことができたのも、私が弁護士として生活困窮者支援に関わっていて、もやいや山友会などの福祉につなぐ場所を知っていたからです。そこでこのような人をたくさん見てきているので、どうすればこの人がこの後生きていけるかというイメージがわくんです。ものすごく寒い夜だったので、あのとき私たちがあの場所を通りかからなかったら彼は本当に死んでいたかもしれない。彼をなんとか福祉につなげられたというのはすごくうれしいですよね。こういうことも弁護士としてのやりがいなんじゃないかと思います。厳密にいえば弁護士の仕事かどうかはわかりませんけどね(笑)。
自由な働き方

──弁護士事務所の経営者として、また一弁護士としての仕事、SAFLANの仕事など、さまざまな活動をしていますが現在はどのような働き方をしているのですか?
当事務所には出社時間やコアタイムなどはありません。何時に来て何時に帰ってもいいし、1週間くらい事務所に来なくても事務所としては問題ありません。そういう意味では自由な勤務環境ですね。もちろん仕事をきっちりやることは大前提ですが。
私の場合はどちらかといえば朝方なので早めに出社して午前中にメールチェックや裁判所に提出する書類作成などやらなきゃいけない仕事はできるだけ終わらせるようにしています。午後は裁判所に行ったり、各種打ち合わせや会議をしたり、書き物をしたり。夕方以降は勉強会や懇親会に出席していることが多いですね。週のうち1日はいわゆるノー残業デーを設け、家で家族と夕食をとれるようにと心がけていますが、達成率は半々くらいでしょうか。なかなか理想通りにはいきませんね。
──ワークライフバランスについてはどうお考えですか?
私は仕事とプライベートのバランスが取れてないと無理なので、いろいろな仕事はみんなで分担して、きっちり休日と余暇の時間を取るようにしています。基本的には土日が休みなのですが、主に子どもと遊んでいます。オートキャンプなどにもよく行きますね。もっとも、SAFLANの活動などで土日に法律相談会や集会、学会などが入ることもあるので毎週必ずというわけにはいきませんが。
自分で時間をコントロールしたい
──働き方に関して大事にしていることは?

自分で自分の時間をコントロールしたいということですね。そもそも学生時代から独立したいと思っていた最大の理由はこれなんです。会社組織の中にいると収入は保障されますが、どうしてもこの点が難しくなりますよね。だから最初に人の動きが流動的な外資系企業に入ったし、その後に弁護士になって事務所を立ち上げたわけです。おかげさまで今はそういう働き方、生き方が実現できているので幸せです。
──いわゆる組織の一員として決められたルールの元で働くというのが性に合わないということでしょうか。
というよりも、基本的に他人にああしろこうしろとあまり強制・干渉したくないし、されたくもないんです。ただ、強制・干渉を拒むということは裏を返せば手厚く手助けしてもらえないということ。私はその方がいいのですが、言われたことはきっちりやって判断自体も相手に委ねる代わりに、もっと手取り足取り面倒を見てもらいたいというタイプの人はうちの事務所は合わないかもしれないですね。弁護士として自立してやっていける人じゃないと厳しい。個人事業主の集まりですからね。
──今後の夢や目標を教えてください。
自分自身の夢や目標、これから成長したいとか何かを成し遂げたいというのはあまりないんですよね。これからも目の前に来た球を打ち返すようなスタンスは変わらないと思います。結果的にはその繰り返しの中で多くの人と出会い、自分の成長にもつながってきたんじゃないかと感じています。ただ最近特に思うのは、先ほども少し触れましたが、「再生産」には意識的に関わっていきたいということです。長男が小学生になったからもしれませんが、自分の次の世代が生きていく世界が気になるんです。
というのは、オウム事件や阪神淡路大震災が起こった1995年くらいから世の中がどんどん悪くなっている、具体的には社会が不寛容になっている気がしているからです。私の子ども時代、1980年代の日本って史上空前のいい時代だったんじゃないかなと思うんですよ。あの空気感を次の世代に少しでも残したいと思うし、その中で平等に成長の機会を与えられて、よりよい社会を作っていけるように健全に育ってほしい。そのお手伝いが少しでもできればいいなと思っています。














